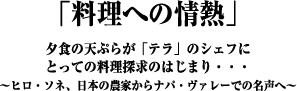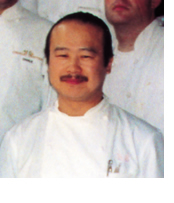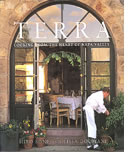|
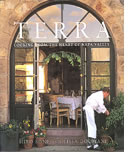
曽根さんの著作
「テラ・ナパ・ヴァレーのハートから生まれた料理」
|
私は日本の宮城県にある小さな農村、一迫町で生まれました。家はこの土地で18代に渡って高級米をつくってきました。
私は4世代、11人の大家族の一員で、我々は皆、農業に携わっていました。
母と祖母はこの大家族のために、毎日、毎食、食事を作っていました。私は小さい頃から食事作りの手伝いを始めました。仕事のひとつは、皆の好物、肉じゃが用のじゃがいもの皮むきでした。また、冬に食べる漬物にする山のような白菜を洗ったり、とうもろこしの皮や、枝豆やその他の豆のさやを、何籠分もむいたりしました。
私が10才の頃のある日のことです。家族が皆、田畑に出ており、私は食事のことが心配になって、自分で作ろうと考えたのです。そして初めて自分一人で、天ぷらを作りました。田畑から帰ってきた家族は、食卓に山と盛られた天ぷらを見て驚き、一つ残らず食べました。これがおそらく、食事を作って人を喜ばせることが自分の喜びにもなることを知った、最初の瞬間だったでしょう。
家族から私は食材を大切にすることを学びました。皆が仕事を終えたあとの田んぼに一人残った祖母が、籾の最後の一粒までを、日が暮れて見えなくなるまで一粒一粒拾っていたことを今でも覚えています。
家では自分達が毎日食べる野菜や果物のほとんどを作っていたので、完全に熟すのを待って収穫を行い、自分達の使いたいものが収穫できるようになるまでは、何か別のものを使う、といったふうでした。いちごを採る時には、一番甘いのを取りあって兄弟喧嘩をしたものです。家に持ち帰ったものより自分達で食べた方が多かったかもしれません。
農家で育つということは、未来の料理人にとって最高のスタートです。素材を尊重することや、ある素材が最上の状態になる時期を知る方法を、そしてそれを育てるのにどれほどの努力が払われているかを教えてくれます。また、明日にはもう無いかもしれないということから、どんなものも無駄にしてはならないということも学ぶのです。
高校1年生の時、私はシェフになる決心をしました。初めは誰にもその事を話しませんでした。父が私には学校の教師になり、農家を継いで欲しいと願っていたからです。卒業の時期が近づいて、自分の将来の希望について両親に話をしました。父は落胆しましたが、祖父は私に味方して皆を説得してくれました。祖父のおかげで私は調理師学校に行くことができました。
私が通うことに決めた大阪の辻調理師専門学校は、現在もなお、世界で最も優れた調理師学校のひとつです。学校がフランスのミシュランの3ツ星シェフ達と交流を持っていることから、そうしたシェフ達が大阪の学校にやって来て授業をしてくれました。それまでフランス料理など味わったことの無かった田舎の少年にとって、それは圧倒されるような出来事でした。
学校は大阪にあり、京都に近く、日本料理の老舗の料理長も大勢、授業に来られました。さらには中国、香港、イタリアのシェフ達の授業もあって、それは申し分のないカリキュラムといえました。
卒業直前にヨーロッパへの研修旅行に参加し、学校へ授業をしに来られたシェフ達のレストランを訪ねました。最も記憶に残る食事はフランス、ヴィエンヌの「ラ・ピラミッド」でのものです。大きい門をくぐって美しい庭に入り、マダム・ポワンと彼女の愛犬の温かい歓迎を受けたことを思い出します。その時の料理もまだ覚えています。
■フォワ・グラのブリオッシュ詰め、ペリゴール産トリュフ入り
■ヒラメのシャンパン蒸し、デュクセル入り
■ウズラのヴェルジュ風味ソース
■サン・マルスラン・チーズ
■フランボワーズのシャーベット
■ガトー・マルジョレーヌ
どの一口のどの味も、私は未だに覚えています。この時の食事の経験が私に将来の方向性を与えてくれました。
辻調理師専門学校を卒業した後、私は東京のイタリア料理店に就職しました。皿洗いから始めてそこで5年働き、スー・シェフまで行きました。この経験から、料理をする上ではすべての段階の仕事が同じように大事であることを学びました。
まだその店で働いている時に友人から電話があって、カリフォルニア・キュイジーヌのレストランでシェフをする気はないかと聞いてきたのです。私は最初、カリフォルニア・キュイジーヌのことなんて聞いたこともないぞ、と思いました。アメリカ人はハンバーガーとホットドッグばかり食べているのだと思っていました。ならば、カリフォルニア・キュイジーヌとは一体何なのでしょうか。しかし友人を信用して面接に行き、そこに職を得ました。それでもまだカリフォルニア・キュイジーヌとは何かわかりませんでしたが、店側はそれを自分の目で見てくるようにと私をカリフォルニアに遣りました。
そのレストランはロサンゼルスにある「スパーゴ」で、私がウォルフギャング・パックに(そして未来の妻リサに)出会った場所です。「スパーゴ」で2ヶ月間研修し、その間すべての部署を回って、できるだけのことを学びました。それは私の人生で最も素晴らしい2ヶ月間でした。その経験でアメリカの料理に関する私の考えは180度変わりました。
研修後、私は東京に帰って「スパーゴ」を開店しました。しかし18ヶ月後にロサンゼルスの「スパーゴ」にまた戻り、ウォルフギャングとともに4年間、彼の店のシェフとして働きました。
1984年、リサの家族のもとへとディナーに向かう途中、私は初めてナパ・ヴァレーを訪れました。その地はふるさとを思い出させ、私は強く心を打たれました。細長くのびた谷間に農業を営む人々が住み、周囲を小高い山々に囲まれていました。自分がレストランを開きたい場所はここなのだということがわかりました。1988年に私たちは夢を実現させ、「テラ」を開店しました。
ナパ・ヴァレーにいることの最大の利点は、小規模な農家や生産者がずらりとそろっていることです。自分が用いる素材をつくる農家と話ができるので、欲しい大きさの時に収穫したり、細かいところまで指定した状態に熟成させた、特別な素材を手に入れることが可能です。これで私の仕事がより楽になるのです。
また、この谷間は地中海沿岸地方の町と似た気候です。そのため私が身につけたフランス料理やイタリア料理の可能性をここで探究することができます。そして幸いなことに、豊富で種類も様々なアジアの食材のあるサン・フランシスコからたった1時間です。ナパ・ヴァレーは私にとって、庭のようなものなのです。
|
|