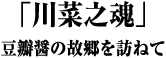 |
||
|
|
||
|
|
6月半ばに念願であった四川省成都を訪れた。成都へは成田空港からの直行便を利用したが、一眠りする間もなく4時間余りで成都空港に到着する。この路線は今年の4月から中国・西南航空によって新しくできたものである。7月からは関空発の便も就航し、こちらは3時間30分とさらに所要時間が短い。以前、日本から成都に行くには上海を経由(上海と成都は1760km離れている)して半日ほどを費やしたようだが、四川省もずいぶんと近くなったものである。 四川省は熊猫(パンダ)の生息地としても有名だが、今回の旅の目的は四川料理の中でも小吃、家常菜を中心に「四川風味」の本質を探ることにある。四川風味を作り出す食材、調味料の数は多く、また四川の各地に特産品があり、永川の豆 |
|
|
|
||
| 一夜明けた成都は朝から激しい雨が降っていた。出発時には降り止んだが、湿った空気は日頃の曇天よりもさらに重い。成都市から100kmほど離れた「 |
 「二荊条」という唐辛子は 15、16cmの長さになる |
|
|
|
||
| 製法はすべて手作りで大きな甕に入れて露天で熟成させる。雨の日は傘をかぶせて雨水を防ぐが、天気の良い日は傘をはずし、夜露を入れ、日中は乾燥させる。毎日、特別製の棒を使って甕の中を混ぜ合わせ、全体を均一にして発酵を促す。この作業はかなりの重労働である。夜露、湿気、天日が不可欠という。最低でも1年以上発酵させたものが市場に出回るが、普通は2年を経たものが多く、最上品は3年ものである。また、一般市場には出荷されないが、ビンテージものの5年熟成の豆瓣醤もある。今回、訪れた「鵑城牌」というブランドの工場では、年間500トンを生産している。 成都に滞在した3日間で120品余りの料理を試食した。その中で印象に残った料理を2、3品挙げておきたい。まず、本場の麻婆豆腐は異なった店で4回食べたが、どの店の味も一様ではない。言い方を変えればそれぞれの店の味なのである。本家の「陳麻婆豆腐店」は西玉龍街197号に移転し、近代的な店に姿を変えていたので、その昔、万福橋にあった頃とは様相が異なる。残念ながら今回は本家の麻婆豆腐が最もレベルが低い印象を受けた。中国の伝統的な味、技術を継承するための商標である「中華老字号」の金看板を持ち、全国的に有名な店ではあるが、店の中でレトルトの麻婆豆腐をお土産にと売り子がテーブルを回る姿からは、我々が思い描いてきた本店への憧憬の念は消え、もはや過去の遺産になってしまっていたのは悲しい事実である。 |
||
|
|
||
 屋台で食べる「回鍋炒飯」。 これで10元(約150円)。 |
変わったところでは裏町にある屋台で「回鍋炒飯」に出会った。豚肉、蒜苗(葉ニンニク)、そして四川料理の魂を加えた典型的な四川風味のチャーハンである。日本でよく知られている「回鍋肉」の入ったチャーハンと理解していただければよい。作り方は、茹でた皮付きの豚肉を小さな角切りにし、豆瓣醤、豆 |
|
|
|
||
| 紙面に限りがあるので詳しくは報告できないが、最後に四川卞氏菜根香烹 |
 成都郊外にある調理師の職業学 校の授業風景。 |
|
|
〈中国料理主任教授 松本 秀夫〉
|
||
|
|
