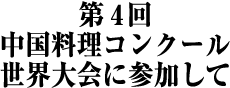 |
||
|
|
||
| プロローグ | ||
|
2002年6月27日〜30日にマレーシア・クアラルンプールで開催された「第4回中国料理コンクール世界大会」に(社)日本中国料理協会から選手として参加する機会を得た。中国料理の世界大会は4年に一度の開催であるが、今回は前の東京大会から2年しかたっておらず、時期としては変則になる。 |
||
| マレーシアに向けて出発 | ||
 団体作品の展示。結果は優秀賞。 |
6月25日早朝に成田空港で全員集合。カウンター前は、食材の詰まった荷物で溢れんばかりである。私の荷物はすでに20kgオーバーで、昨日は伊丹空港で一悶着終えたところである。器に使用するミラーガラスはクアラルンプールの空港まで手荷物にして抱えた。 日本チームのメンバーとは出発の約1カ月前に顔合わせをし、混成メンバーでチームを組む団体作品の展示について検討した。「 |
|
| 料理展示の準備が始まる | ||
同日の夜、マレーシアに着く。かなり気温も高く、湿気も多い。主催者側の好意でマレーシア料理による遅い夕食をいただく。驚いたのは料理に豚肉、それに心配だった豚の耳も出てくるではないか。ム・・・・・。取りあえず急いで日本から持参した材料を冷蔵庫に入れて翌日に備える。 26日の早朝、フリーマーケットに行く。マーケットは香港などの市場と大差はないが、肉屋には豚肉が並んでいる。ム・・・・・。それと現地での食材を心配して日本から数多く調達、持参したが、このマーケットでほとんどのものが揃う。20kgの超過荷物は何だったのか。ム・・・・・。 団体展示のディスプレイは27日の午前9時がタイムリミットである。会場では各国チームの選手たちも慌しく準備にかかっている。ここで差をつけられたのは展示台の背景など、料理や細工物以外の飾りつけである。マレーシアチームは地元の利もあるが、中国、香港、シンガポールなど他のチームもすごく凝っていて、大掛かりなディスプレイは見せる料理を充分アピールしている。会期中の見学者を4万人と見込んでいる主催者側の期待に応えるべく、作品が次々に完成し、世界大会の雰囲気が徐々に盛り上がってきた。 |
 会場となった「太子世界貿易 中心」の展示風景。 |
|
| コンクールに挑む。そして審査が・・ | ||
|
|
29日の午前9時に個人作品のコンクールが始まる。私は6組目でエントリー番号は58番。普段になく緊張しているが、授業などで人から見られるのは慣れているので心配はない。ブースは約1坪のスペースで、共通の器具はまな板が1枚だけである。長方形の新しいまな板はすべりやすく、包丁の動きが鈍る。制限時間は90分で、タイムオーバーはもちろん減点の対象となる。 作品は審査規則に従い、2種類を作る。ひとつは試食用で2人分の 翌30日の夕刻にレセプションを兼ねた審査の発表が行われた。マレーシアの民族的なショーが始まり、会場は華やかな雰囲気に包み込まれた。テーブルでは広東語が飛び交い、特有の賑やかさでお祭り気分が一層盛り上がる。 宴も最高潮に達する頃に、いよいよ審査の発表が始まった。緊張の一瞬である。 自分の作風を旨とした |
 個人作品の 出来ず、悔いが残る。 |
| 世界大会で感じたこと | ||
果蔬彫部門に出品した台湾代表の女性調理師が印象に残った。年齢は40歳過ぎと思うが、観戦していた人から普段は点心を専門にしていると聞いた。作品は大菊5輪を作成していたが、制限時間3時間の中で一から始め、完成度も高く、素晴らしい作品だった。多くの中国人は大作を狙い、時間外に作成したものを使うなど違反行為も見受けられたが、この台湾の人はモチーフも決して強い印象を与えるものではないが、技術的なレベルと真摯に挑む姿に感銘を受けた。 今までに経験したことのない刺激的なコンクールであった。このような機会を得て、中国料理に限らず料理の技術レベルは、世界各地で日々向上していることを痛切に感じた。個人的には、 最後に、世界大会へ参加することができ、よい経験を与えていただいた日本中国料理協会、および勤務先である学校の関係各位に御礼を申し上げ、また同行した選手全員に出会えたことに感謝したい。 |
||
|
〈中国料理主任教授 日高 哲夫〉
|
||
|
|

