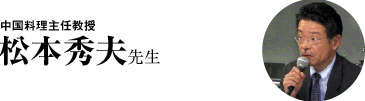
| 日経レストラン メニューグランプリは今年で11回目ですが、大会の認知度はどの程度だとお考えですか? 今大会への応募数は529作品でした。かなりの応募数であったと感じています。メニューグランプリ開催の告知は日経レストラン誌上及びHP上で行っているのですが、以前の参加者の口コミもあってかなり底辺が広がってきているようです。 去年から決勝戦の形式を変えましたね。 昨年から国内最大の飲食業界向け展示会「ホテレス・ジャパン」の会場で、公開形式にして来場者と一体になって盛り上がれる決勝戦にしようと試みています。もちろん、パフォーマンス部分の演出というのは本来の趣旨ではないのですが、公開形式で行う以上より臨場感のあるスタイルにしていきたいと思います。今後の課題ですね。 グランプリ獲得の宣伝効果は大きいのですか? グランプリ獲得の宣伝効果は、非常に大きいです。例えば、第1回大会でグランプリを獲得した株式会社『ちゃんと』ですが、その時のグランプリ受賞作品が大きな話題を呼び、一躍新興外食企業として名を馳せるようになりました。まさに、メニューグランプリでのサクセスストーリーと言えるでしょう。もちろん、グランプリ受賞作品を直接商売に結びつけるか、もしくはそれをバネにご本人自身が更なる飛躍をするかは、グランプリ受賞者それぞれ違います。ただ、本人にとっても、作品にとっても、本人たち思っている以上に結果がついてきているのは確かだと思います。 今回のグランプリ作品についてはどう思われましたか? 三島氏の「サムゲタンでイタリアン」は、韓国料理であるサムゲタンにバジルソースを加えることで、見事にイタリア料理の味に変化しました。韓伊の融合という新たな視点でのイタリア料理で面白い作品だったと思います。なによりもプレゼンテーションが良かったですね。土鍋で提供することや、三島氏自らが取り分けたり、鶏の中からお米が出てきたりと、見た目に楽しませてくれる作品でした。 あらためて、グランプリの審査ポイントをお聞きしてもいいですか? メニューグランプリは、「料理が面白い」「味が良い」というのはもちろんとして、実際にレストランで提供した時に、“その金額でお客様に満足してもらえるのか”という点が大きなポイントです。美味しいのだけれど「値段が高い」、「仕込みが複雑で現場のラインに乗らない」では駄目なのです。あくまで、 “実用性の高さ”というのが審査の基準になります。細かく言えば、「価格」「仕込み」「プレゼンテーション」「味」「テーマ性」ですね。 今回のグランプリ応募作品全体の印象はいかがでしたか? 応募作品を個別に見てみると、日本料理が少なかったように感じました。日本料理は、全般的に健康的なイメージがあるので、メニューグランプリに応募するための切り口が見つからなかったのかなと感じました。テーマによってはオリジナリティをだすのが難しいのかもしれませんね。 全体的には、どの作品もレストランで十分提供できるだけの水準でした。ただ、「サムゲタンでイタリアン」や「キムチの王様」と比べると「オリジナリティ」「驚き」「感動」が少し物足りないなと感じます。私たちが驚くようなアイディア溢れる料理、ユニークな発想の料理がどんどん応募されることを期待しています。 卒業生の活躍は嬉しいですね。 毎回、多くの卒業生が応募されています。決勝や準決勝で卒業生の姿を目にすることができるのは、非常に嬉しいことです。上位まで届かなくても、惜しいなと感じる料理はたくさんありますので、グランプリを目指してあきらめずに挑戦してもらいたいですね。 |